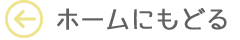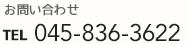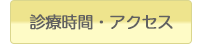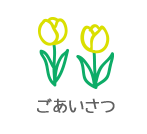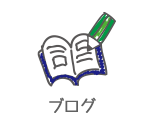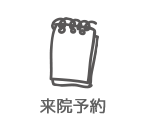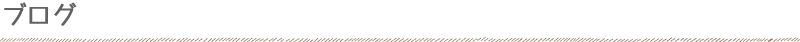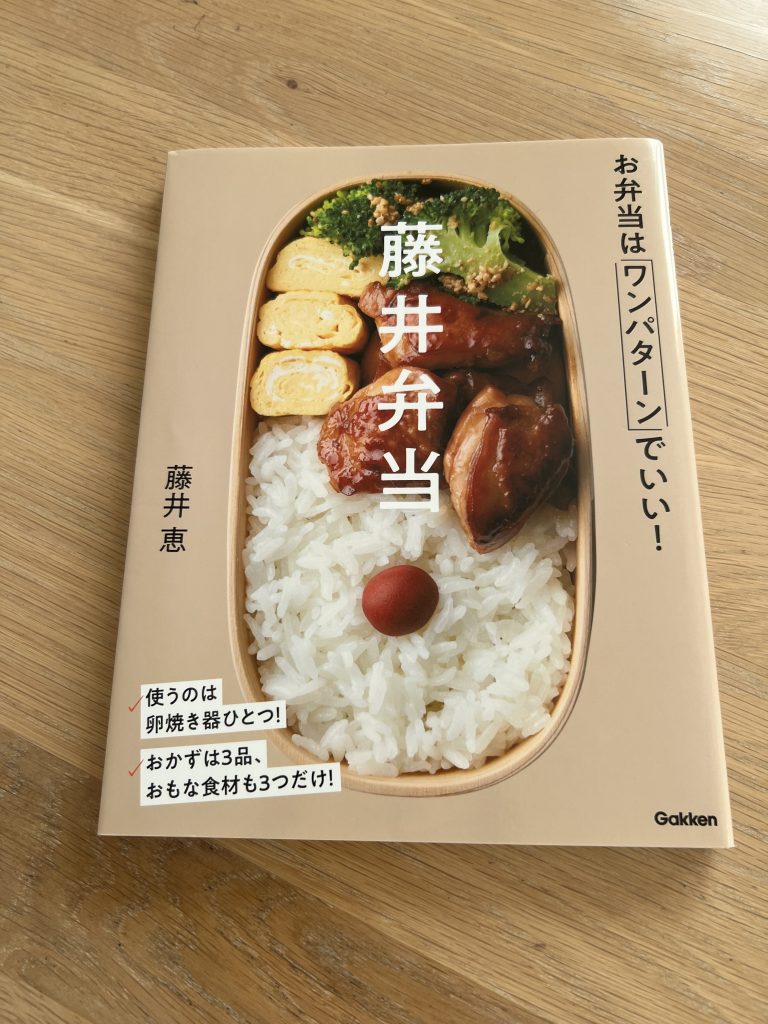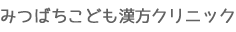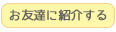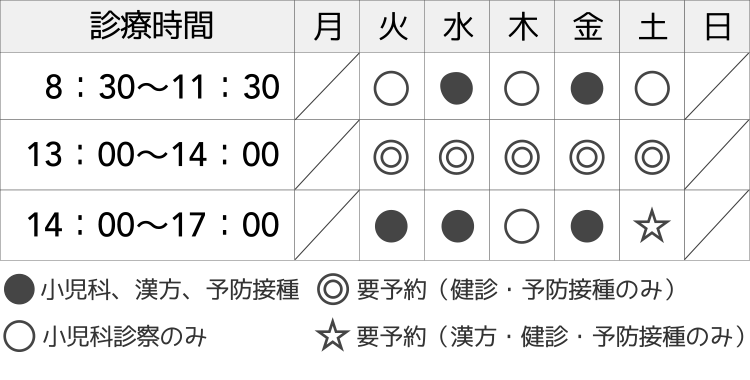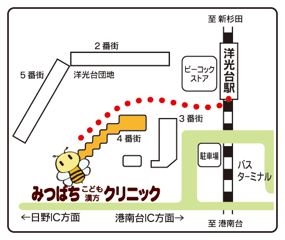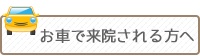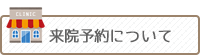「私を殺さないものは、私をいっそう強くする。」
Was mich nicht umbringt, macht mich stärker.
ドイツの哲学者・ニーチェの言葉
致命傷にならない程度のダメージは全て、その人を強くする。
これって、色々なことに当てはまると思います。
例えば、筋トレ。
筋トレで筋肉にダメージを与えると、筋肉はもっと強くなる。
例えば、ワクチン。
ワクチンで体に病的な刺激を与えると、免疫力がもっと強くなる。
例えば、ポリフェノール。
ポリフェノールは軽い毒なのですが、ポリフェノールを摂取すると体の解毒機能を鍛えてくれる。
(院長は毎日赤ワインとコーヒーでポリフェノールを摂取中)
そして、この法則はもちろんメンタルにもあてはまります。
「私を殺さない程度の精神的ダメージは、私をいっそう強くする。」
だから、今とても辛く悲しい思いをしている人は、
将来もっと強くなれます!