こんにちは、まつざわです。
残暑が長く、さわやかな秋が待ち遠しくて、10月初旬中央アルプ
めざすは、駒ケ岳ロープウェイで標高2612mまで上がり、紅葉
気温15℃前後の肌寒い中、木曽駒ヶ岳をめざして急斜面を登るハ
山の天気は変わりやすく下りのロープウェイは白い雲の中で、まさ
秋の味覚も楽しみながら、近場の秋も満喫したいと思ってます!


(2022年10月19日)
こんにちは、まつざわです。
残暑が長く、さわやかな秋が待ち遠しくて、10月初旬中央アルプ
めざすは、駒ケ岳ロープウェイで標高2612mまで上がり、紅葉
気温15℃前後の肌寒い中、木曽駒ヶ岳をめざして急斜面を登るハ
山の天気は変わりやすく下りのロープウェイは白い雲の中で、まさ
秋の味覚も楽しみながら、近場の秋も満喫したいと思ってます!


(2022年9月16日)
今年度の当院におけるインフルエンザワクチンの接種は10月から12月末までを予定しています。
ワクチンの入荷状況によって変更があるかもしれませんので、最新の情報をホームページで確認してください。
予約はインターネットのみで受け付けます。予約開始は9/28(水)です。1週間先までの予約をとることができます。(例)10/5の予約は9/28の0:00から可能。
予約ができるのは当院の診察券をお持ちの、生後6ヶ月から中学3年生までの方です。
【インフルエンザワクチン外来】
水曜日 午後2:00〜4:30 土曜日 午後3:00〜3:45
ワクチンの予診票を事前に記入してお持ちください。
予診票はホームページからダウンロードできます。
___________________________________________________________
【当院においてインフルエンザワクチン接種を推奨する方】
●生後6カ月以上5歳未満の乳幼児
●気管支ぜんそくなどの持病を持っている方
●乳幼児の家族、受験生など、インフルエンザにかかりたくない事情のある方
【インフルエンザワクチンの接種回数】
当院ではWHO方式を採用します。(従来の接種回数とは異なります。)
生後6ヶ月〜3歳未満 : 2回(1~4週間あけて)
3歳以上〜9歳未満:昨年インフルエンザワクチンを接種した人は1回
昨年インフルエンザワクチンを接種していない人は2回(1~4週間あけて)
9歳以上 : 1回
【インフルエンザワクチンの接種料金】
1回 3700円(税込)
【重要なお知らせ】
当院では、インフルエンザワクチンと他のワクチンの同時接種を行いません。
また、インフルエンザワクチン接種でご来院された場合、車でいらしても駐車券のサービスはありません。
(2022年9月16日)
こんにちは。看護師のながさきです。
9月に入ったと言うのにまだ暑い日が続きますね(^_^;)
この夏、我が家は3年ぶりに海に行ってみました。(私はテントの
波を見ているだけで随分と癒されたように思います。
色々な事に気を張らざるを得なかった数年でしたし、忙しくて疲れ
身体と心の健康のベースをあげていられるよう、
皆さまもちょっとひと息の時間大切に過ごしてください。
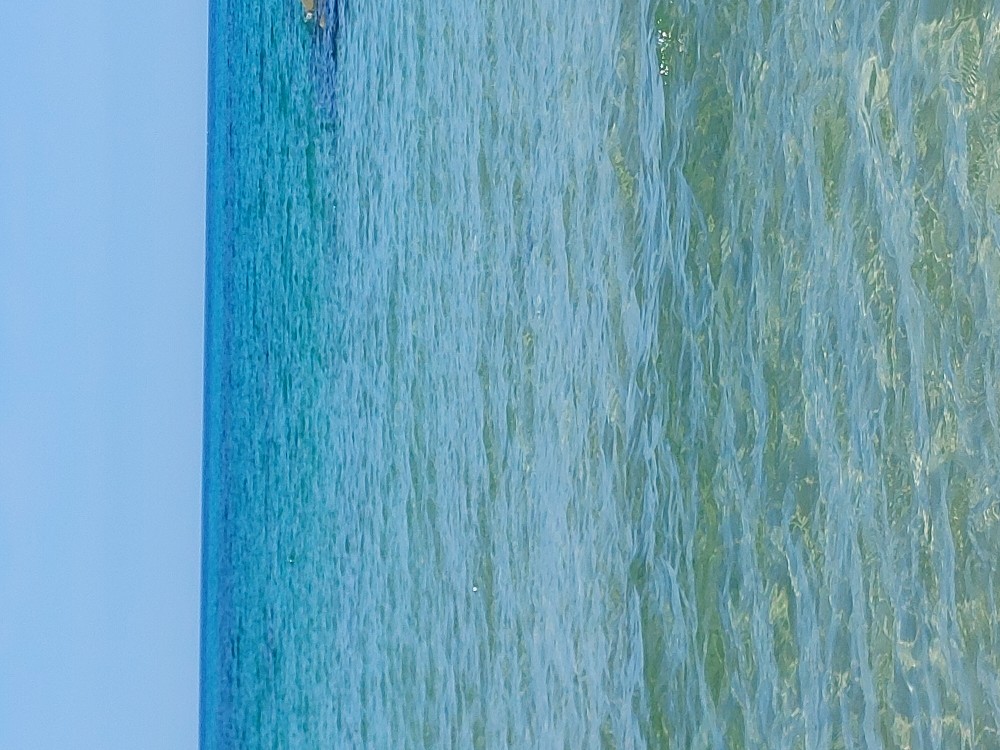
(2022年7月27日)
こんにちは。スタッフのこんどうです。
過去最も早い梅雨明けが発表され、
本格的な夏を迎えて1ヶ月ほど経ちましたが、
みなさんいかがお過ごしでしょうか?
この間、何年かぶりに横浜スタジアムへ行って来ました!
久しぶりなこの光景(^^)
どこのチームを応援してるとかではありませんが、とても楽しい時


(2022年6月16日)
大変長らくお待たせしました。
日本脳炎ワクチンの入荷がようやく安定したので、3回目以降の方の接種も行います。
インターネットでも予約が取れるようになりました。
ご希望の方はインターネットかお電話でご予約ください。
(2022年6月15日)
こんにちは、スタッフのやまざきです!
梅雨に入りじめじめ湿気がイヤな季節です…
そんな梅雨の晴れた日に、ずっとやりたかった梅酒を初めて作って
スーパーで青梅が出る季節になると毎年、
今年こそは!!と思っていたのですが、いつも時期を逃してしまい
今年はやっと作ることができました!
梅を洗ったり一粒づつ拭いたりしているだけでも梅のいい香りがし
半年後?一年後?がとても楽しみです!

