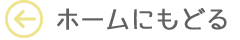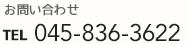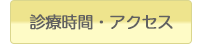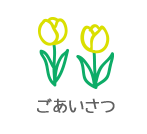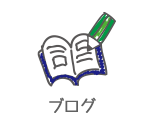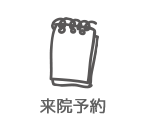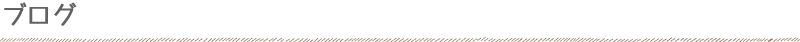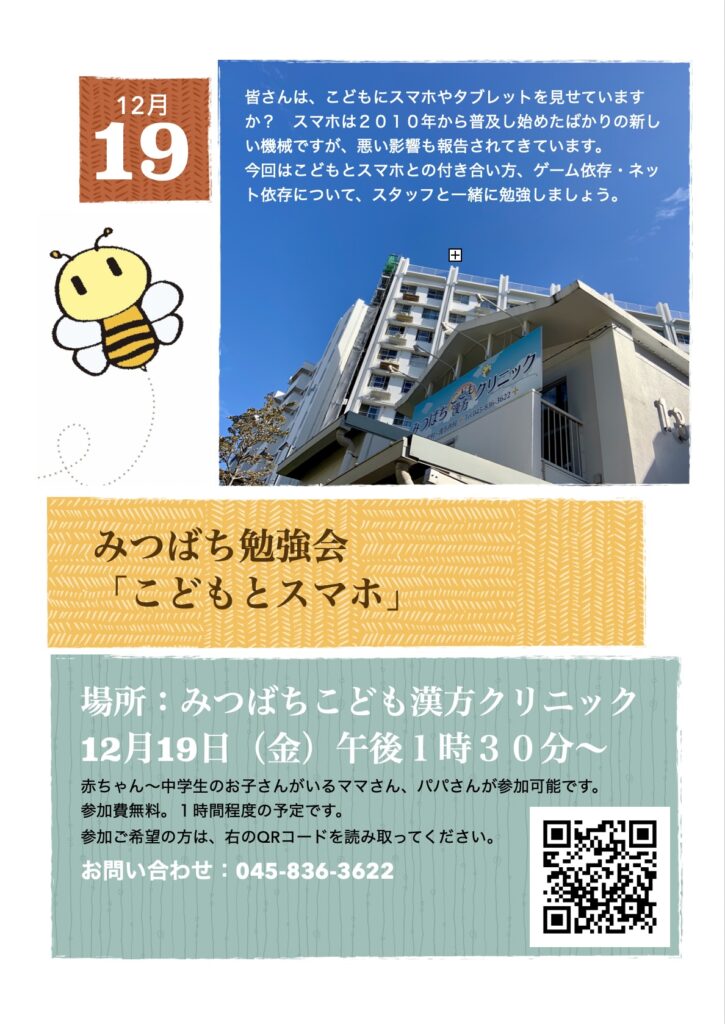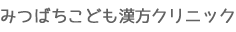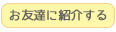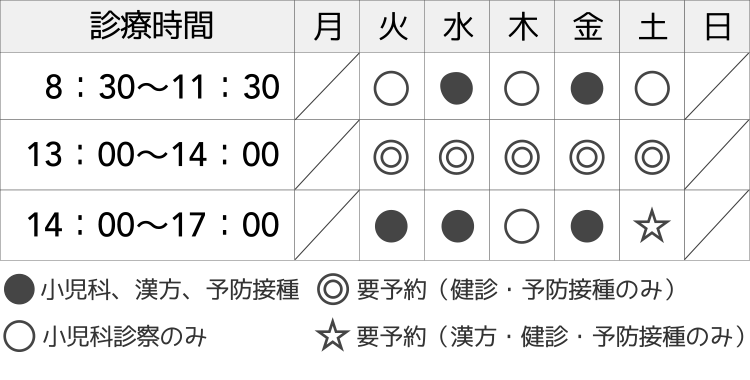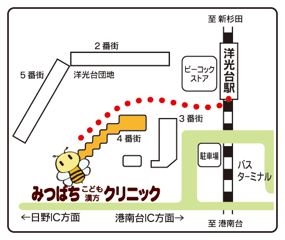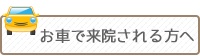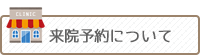「養生訓」とは:
江戸時代、儒学者の貝原益軒(かいばらえきけん)が83歳の時に出版した健康長寿の心得。当時のベストセラーになりました。(当時の平均寿命は50歳未満だったそうです。)
養生訓には、現代でも参考になるような教えが書かれています。
_______________________
「養生の術はまず心気を養うべし。心を和にし、気を平らにし、怒りと欲を抑え、憂いや思いを少なくし、心を苦しめず、気を損なわず。」
心が穏やかであることが健康長寿の基本として最初に取り上げられています。非常に納得ですね。
心を穏やかにするために私が一番大切だと思っているのは、
「自分がやるべきこと、自分ができることをやる」ということです。
他人のやるべきこと、他人の課題には手を出さない。
人の手に負えないような不幸や不運が存在することも理解する。
自分からストレスを手放す。
私は私ができることしかできないけど、私ができることが誰かの役に立つこともあります。
そうそう、「養生訓」にはこんな素敵な教えもあります。
「すべてのこと十分によからんことを求れば、我が心のわずらいとなりて楽しみなし。いささか良ければ事足りぬ。十分によからんことを好むべからず。」
:全てに完璧を求めてはいけない。多少でも気に入ればOK。
パートナーにも子供にも完璧を求めてはいけません(^^)